
|

|
|
|
|
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル ・コラム ・みる・よむ・きく ・インタビュー ・解説 ・こぼれ話 特集 ・環境 ・欧州 ・コラム ・アフリカ ・沖縄/日米安保 ・社会 ・人類の当面する基本問題 ・みる・よむ・きく ・橋本勝の21世紀風刺絵日記 ・外国人労働者 ・中南米 ・反貧困 ・反戦・平和 ・政治 ・農と食 ・市民活動 ・中国 ・国際 ・検証・メディア ・文化 ・遺伝子組み換え/ゲノム編集 ・医療/健康 ・アジア ・イスラエル/パレスチナ ・難民 ・米国 ・生活 ・核・原子力 提携・契約メディア ・AIニュース  ・司法 ・マニラ新聞   ・TUP速報    ・じゃかるた新聞 ・Agence Global ・Japan Focus  ・Foreign Policy In Focus ・星日報 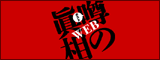 Time Line ・2021年01月07日 ・2021年01月06日 ・2021年01月05日 ・2021年01月04日 ・2021年01月03日 ・2021年01月02日 ・2021年01月01日 ・2020年12月31日 ・2020年12月30日 ・2020年12月29日 |
環境 ベトナム・ブンアン2石炭火力発電事業から撤退を!FoE Japanが声明を発表 「国際環境NGO FoE Japan」は昨年12月29日、国際協力銀行(JBIC)がベトナム・ブンアン2石炭火力発電事業に6億3,600万米ドルの融資支援を決定したことについて、同事業に関係する企業や金融機関に対し、同事業から撤退するよう求める声明「国際協力銀行によるベトナム・ブンアン2石炭火力発電事業の支援決定に強く抗議」を発表した。(藤ヶ谷魁)(2021/01/07 08:23) 欧州 Sciences Poを指導してきたフランスの大物政治学者が義理の子供への性的虐待で糾弾される 30年前の犯罪を子供が暴露した本「La Familia Grande」で刑事事件に フランスのシアンスポ(Sciences Po ,政治学院)と言えば、エリートを輩出する名門校として世界的に知られていますが、その政治学院の運営母体である国立政治学財団(FNSP)の政治学者が義理の子供への性的虐待で告発されています。渦中にいるのはオリビエ・デュアメル氏で、義理の子供に本の中で糾弾され、政治学院の関連財団の職を辞したばかり。放送局Europe1のコメンテイターも辞職したとされます。(2021/01/06 22:09) コラム 現代に関東軍がいたら、何をするか? 北方領土上陸だろう・・・ 冷戦時代に「第三次大戦はこう始まる・・・」的な本が出版されていたが、その1つは北海道にソ連が上陸するという想定のものだった。結果的にはソ連は上陸しなかった。とはいえ、安倍政権の途方もない接待や交渉をあざ笑うかのようにロシアは第二次大戦中に接収した北方領土の日本返還へのハードルを憲法改正によって一段上げたのだった。(2021/01/06 13:04) コラム 有事に弱い政権が続く 昨年9月に終焉した安倍政権の特徴の1つが有事に弱い、ということだった。民主党政権の福島原発事故処理などを最大限、集票のアピールに使ってきた安倍晋三だが、新型コロナウイルスの処理では対応が後手後手に回っただけでなく、配布までに1か月以上時間がかかった上に製品の質でも問題が起きた「アベノマスク」で自らの脆弱さを見せ、その結果、支持率がついに上がらなくなって辞任につながった。(2021/01/06 12:50) アフリカ 【西サハラ最新情報】 初日はのぼった!エジプトがモロッコ西サハラ領有権拒否 平田伊都子  新年早々、物騒な話ですみません。 昨年末から引きずっている、毒殺未遂されたロシア反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイが、横領容疑で再逮捕。 アメリカ・ナッシュビルで、9・11テロ事件紛いのクリスマス・テロ爆破事件、イエメン・アデン空港で、新政権閣僚たちがタラップを降りた直後に爆破テロ、エチオピア内戦、、、などなど、昨年から引きずっている血なまぐさい事件は未解決のまま、新年を迎えました。 一番混乱しているのはアメリカです。 退陣寸前にトランプ氏が言った<モロッコ領有権承認>発言は、次期アメリカ政権が即刻廃棄処分しなければならない、大国際問題になってしまいました。 トランプ暴言はモロッコのメデイアでも反論を招き、反論を許さないモロッコ王室は粛清に取り掛かったようです(2021/01/05 19:17)
新年早々、物騒な話ですみません。 昨年末から引きずっている、毒殺未遂されたロシア反体制指導者アレクセイ・ナワリヌイが、横領容疑で再逮捕。 アメリカ・ナッシュビルで、9・11テロ事件紛いのクリスマス・テロ爆破事件、イエメン・アデン空港で、新政権閣僚たちがタラップを降りた直後に爆破テロ、エチオピア内戦、、、などなど、昨年から引きずっている血なまぐさい事件は未解決のまま、新年を迎えました。 一番混乱しているのはアメリカです。 退陣寸前にトランプ氏が言った<モロッコ領有権承認>発言は、次期アメリカ政権が即刻廃棄処分しなければならない、大国際問題になってしまいました。 トランプ暴言はモロッコのメデイアでも反論を招き、反論を許さないモロッコ王室は粛清に取り掛かったようです(2021/01/05 19:17)
沖縄/日米安保 「踏み越える専守防衛―急浮上した敵基地攻撃と第5次アーミテージ・ナイ報告を読み解く」~1月8日、新外交イニシアティブがオンラインイベント開催 安倍政権が置き土産的に残していった敵基地先制攻撃能力保有論。昨年中に同能力保有容認という形には至らなかったが、12月18日には新ミサイル防衛システムの整備やスタンド・オフ防衛能力の強化が閣議決定され、実質的な能力保有が進められている。同時に、アメリカのシンクタンクが12月7日に「第五次アーミテージ・ナイ報告書」を発表。中国の脅威に対抗するためとのお題目で、日米の同盟関係を「相互依存」にまで高めるべきと提唱されており、今まで以上に自衛隊が米軍に組み込まれていくことが危惧される。新外交イニシアティブ(ND)では、今年最初のイベントとして、2021年1月8日(金)19:00より、「踏み越える専守防衛―急浮上した敵基地攻撃と第5次アーミテージ・ナイ報告を読み解く」と題したオンラインイベントを開催し、今後の日本外交・防衛政策のあるべき姿を議論する。イベントの概要等は以下の通り。(2021/01/05 17:05) 社会 < a care-worker’s note・6> 介護職は“ケアの倫理”によってエンパワーされるか? 転石庵茫々 2020年は、コロナ禍により予想もしなかった出来事が次々と起こり、今までごく普通にあり、特に注目もされていなかったにもかかわらず、実は、社会を支える上で欠かせない職業であった、スーパーの店員、清掃員、医師や看護師、介護労働者などのエッセンシャルワーカーと呼ばれている人たちへの関心が高まり、コロナ禍の危険の中で、他者のために働く、その姿勢に<ケア>の精神を、その行為の背景に<ケアの倫理>ともいえる職業倫理を感じ取った人も多いと思います。コロナ禍が高まり長期化することもはっきり見えてきた、2020年7月に文学系の月刊誌『群像』8月号に英文学者小川公代氏による『“ケアの倫理”とエンパワメント』という文章が掲載され、時宜を得たテーマと思いもよらないハードな切り口とソフトな語り口で評判になりました。(2021/01/05 10:52) コラム 古いソ連のオートバイの修復動画に心動かされた 年末、YouTubeで久々に心を動かされる動画に出会った。ぼろぼろになったソビエト時代のオートバイを工場で黙々と修復していく動画である。動画の主人公はほとんど手元しか露出せず、修復のプロセスが1つ1つ、美しいカットとよく採られた音声で見ることができる。印象深いのはバイクの鉄に付着した錆や汚れを1つ1つ様々な溶液につけて溶かし、その後、鑢をかけて綺麗にしていくのだが、もちろん、おそらく腐食が進みすぎて、全部取り変えたパーツも少なからずあったろう。(2021/01/04 13:41) 人類の当面する基本問題 (36)人類文明の転換期日を象徴する「3.11」と「9.11」 今年は10年、20年の節目の年 落合栄一郎 2021年3.11日は、コロナ禍のパンデミックがWHOによって宣言されてちょうど1年、東日本大震災、それに伴って発生した福島原発事故から10年の節目の年になります。そして半年後の9.11日は、アメリカ本土(ニューヨーク、ワシントン)でのいわゆる同時多発テロ事件から20年目、そして今より半世紀ほど前の1973年9.11日は、チリでの選挙で選出された大統領アイエンデ をピノチェット率いる軍事クーデターで倒すという事件。これは、実は、これによって政権を獲得した側が、アメリカの後押しで、経済の「新自由主義」的施策を始めたという画期的事件で、経済の「新自由主義」の実現(理論はもっと前から)発祥点と考えられている。こう見てくると3.11、9.11は、ともに人類文明の転換期日を象徴しているようである。(2021/01/03 16:33) 欧州 核兵器禁止条約とイタリア~チャオ!イタリア通信  今年1月22日に核兵器禁止条約が発効しますが、日本もイタリアもまだ条約に署名していません。イタリアで核兵器禁止について、政治上何も動きがないわけではないのですが、イタリアはNATO加盟国であり、NATOの中でも「ニュークリアシェアリング」(核兵器を共有すること。NATO内における核抑止力の政策上の概念)の参加国であるということに制約を受けています。ロンバルディア州のゲーティ基地とフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のアヴィアーノ基地には、アメリカの核爆弾B61-4が50個保管されていると言われています。(サトウ・ノリコ=イタリア在住)(2021/01/03 15:30)
今年1月22日に核兵器禁止条約が発効しますが、日本もイタリアもまだ条約に署名していません。イタリアで核兵器禁止について、政治上何も動きがないわけではないのですが、イタリアはNATO加盟国であり、NATOの中でも「ニュークリアシェアリング」(核兵器を共有すること。NATO内における核抑止力の政策上の概念)の参加国であるということに制約を受けています。ロンバルディア州のゲーティ基地とフリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州のアヴィアーノ基地には、アメリカの核爆弾B61-4が50個保管されていると言われています。(サトウ・ノリコ=イタリア在住)(2021/01/03 15:30)
みる・よむ・きく 久松健一著「本気で鍛えるフランス語 広げる中級編」 音源はどこへ?? 以前、久松健一氏による「動詞宝典」という動詞の活用をすべてのページにつけた動詞中心の参考書について絶賛する記事を書きました。フランス語を始めとして、イタリア語やスペイン語などの古代ローマ帝国から派生した言語は動詞の活用が言語習得に大きな重要性を持っています。しかしながら、第二外国語の一般教養の課程で学校教育で習得できる動詞が実際にはごく少数であるという理想と現実がありました。久松氏の参考書はその溝を埋めるものでした。「本気で鍛えるフランス語 広げる中級編」は昨年古書店で新品同然のものを購入して手に取って読んでいますが、ドリル式になっていますが、骨子はやはり動詞に焦点が当てられており、472の動詞が解説されています。(2021/01/02 18:02) 橋本勝の21世紀風刺絵日記 355回 地球憲法は象牙をハンコに使うことを許さない 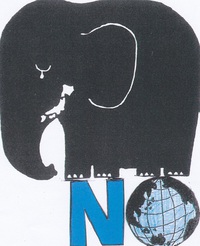 ハンコという文明は日本人の生活の中で 重要なものとしてあり続けてきた だが今、デジタル化とやらでそのハンコが 不要なものにされつつある(2021/01/02 14:44)
ハンコという文明は日本人の生活の中で 重要なものとしてあり続けてきた だが今、デジタル化とやらでそのハンコが 不要なものにされつつある(2021/01/02 14:44)
外国人労働者 コロナ禍で追い込まれる在日外国人~オンラインイベント「国際移住者デー2020」② 「移住者と連帯する全国ネットワーク」がオンラインで開催した「国際移住者デー2020」では、コロナ禍を受けて取り組まれた「移民・難民緊急支援基金」による支援を受けた外国人、そして支援団体関係者によるリレートークも行われた。新型コロナウイルスの感染拡大の中、日本人以上に困難に直面しながらも、なかなか目を向けられない在日外国人の実態が明らかになった。日本社会が抱える様々な不公平や矛盾。コロナ禍の今だからこそ改めて考える必要がある(村田貴)(2021/01/02 06:22) コラム マリーヌ・ルペンの年末のメッセージ 2021年はフランスの政治に重要な1年になるだろう かつて国民戦線(FN)だった極右政党は今、国民連合(RN)に名前を変えて、党首にマリーヌ・ルペンを頂き、政治勢力の躍進を続けている。2022年はフランスの大統領選の年であり、2017年にエマニュエル・マクロンに敗れた彼女は来年こそと勝負をかけてくるだろう。その気持ちは12月の暮れに彼女が発信したメッセージに込められていた。その言葉の中で、2020年は悲惨な年であったが、COVID-19以上に犯罪者のイスラミスト勢力が繰り返しフランスで仲間をテロで斃したと強調した。彼らにフランスを壊させてはならないと訴え、2021年には地方選挙があるので、皆さんの意志を見せてくださいと訴えた。(2021/01/01 11:37) 中南米 ラテンアメリカ社会科学の失楽園 マルコス・ロイトマン・ローゼンマン/ 訳:山端伸英 以下に1973年、クーデタを機に亡命し、スペインでラテンアメリカの民主化を追っている政治学者マルコス・ロイトマン・ローゼンマンのメキシコの新聞「ラ・ホルナダ」2020年2月23日に寄稿したエッセイを翻訳した。ラテンアメリカの日常でこれを見ても、その晦渋さはぬぐえない。またサパティスタ評価も、現在のメキシコの状況との齟齬を持っている。ロイトマンの評価は、98年ころからのサパティスタ指導者の「国民国家」への傾斜についてフォローされていない。それでいながら政治学次元での従属論以降のスタンスを切り開こうとする姿勢をやはり評価せざるを得ない。なお2020年12月28日に改めて彼は「ラテンアメリカ社会科学の過去と未来」というコラムを発表している。それについても翻訳する予定でいる。(2021/01/01 10:05) 外国人労働者 コロナ禍で明らかになった日本の国際人権意識と市民社会の取組~オンラインイベント「国際移住者デー2020」① 今年はまさに新型コロナウイルス一色の1年だった。コロナ禍により、様々な問題点が浮き彫りになった1年とも言えるが、日本社会が抱える大きな問題点、とりわけコロナ禍により改めて直視する必要に迫られているのが在日外国人の問題ではないだろうか。在日外国人支援活動に取り組む「移住者と連帯する全国ネットワーク」は、国連が2000年に定めた「国際移住者(移民)デー」に合わせ、毎年、移民・難民の現状について考えるためのイベントを開催してきた。今年はコロナ禍ということもあり、12月19日にオンラインで「国際移住者デー2020」を開催。イベントでは、移住連が取り組んできた「移民・難民緊急支援基金」の報告や、困難に直面する在日外国人らからの切実な報告が行われた(村田貴)(2020/12/31 17:54) コラム フランス語の辞書を読む 私は今年に入って翻訳書を出してから、泥縄式的に辞書を引く、というより日常的に毎日読むようになった。先日、その経緯については書いたのだが、今回は私が目下、愛読している辞書について。過去に使ってきた辞書は私の場合、白水社のものと旺文社のものが多かった。今回、私が愛読しているのは旺文社のNouveau Petit Royal(第三刷)という仏和辞典である。愛読している、というより実質的にノートにほとんど丸写ししているのだが、と言ってもアルファベットのAから順番にやるというようなことはできないし、飽きてしまうので、私の場合はサイコロ賭博のようにぱっと開いて気の向いた単語から書き写していき、筆写が終わったら蛍光ペンでしるしを付けて置く。(2020/12/31 12:32) みる・よむ・きく 米国の核と食糧の傘に守られた日本の危うさに警鐘 大野和興・天笠啓佑『農と食の戦後史』 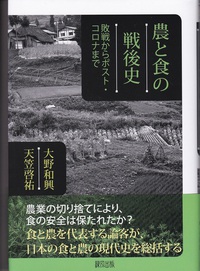 戦後75年の日本の農と食の現在地を確認し、私たち一人ひとりがこの問題にどう向き合うべきかを、二人のジャーナリストが現場取材を踏まえて語り合った本書は、すでに日刊ベリタでくわしく紹介されている(注)が、私はそこではあまり多く触れられていない点について考えてみたい。それは、「戦争と食糧は切り離せない」という大野さんの指摘である。具体的には、日本の食糧農業政策が日米同盟とセットになって進められてきた事実である。(永井浩)(2020/12/30 11:44)
戦後75年の日本の農と食の現在地を確認し、私たち一人ひとりがこの問題にどう向き合うべきかを、二人のジャーナリストが現場取材を踏まえて語り合った本書は、すでに日刊ベリタでくわしく紹介されている(注)が、私はそこではあまり多く触れられていない点について考えてみたい。それは、「戦争と食糧は切り離せない」という大野さんの指摘である。具体的には、日本の食糧農業政策が日米同盟とセットになって進められてきた事実である。(永井浩)(2020/12/30 11:44)
|
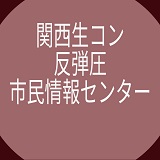 |
| Copyright (C) Berita unless otherwise noted. |
| よくある質問 | お問い合わせ | 利用規約 | 各種文書 | 広告掲載 | 記事配信 | 会社概要 | About us |
■久松健一著「本気で鍛えるフランス語 広げる中級編」 音源はどこへ??
■語学の参考書と辞書の関係
■再開のための哲学 マチュー・ポット=ボンヌヴィル著「もう一度・・・やり直しのための思索」(Recommencer)