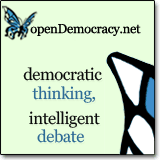 【openDemocracy特約】イスラエルとその戦争犯罪に対して、欧州の左翼はわれわれレバノン人を支持している。ありがとう。すばらしい。大地を焦土化し、兵士も、赤ん坊も大人も区別なく、国土と空域に対する圧倒的な技術的蛮行に直面して、レバノン人はすべての支援を必要としている。
【openDemocracy特約】イスラエルとその戦争犯罪に対して、欧州の左翼はわれわれレバノン人を支持している。ありがとう。すばらしい。大地を焦土化し、兵士も、赤ん坊も大人も区別なく、国土と空域に対する圧倒的な技術的蛮行に直面して、レバノン人はすべての支援を必要としている。
だが、定義によれば進歩的な左翼が、もし米国の外交政策と米国自身への憎しみだけが動機となった一般概念で満足しているのではなく、その状況の特異性を把握しているなら、もっと好ましい。米国の政策、特に中東における政策は確かに卑劣であるが、具体的な国民への献身的愛情は、「大義」への忠誠より優先するように、レバノンとその他の国と国民に対する愛情は、米国とその政策を嫌うことより重要であるべきである。
デモ隊がジョージ・W・ブッシュやトニー・ブレアー、イスラエルのエフド・オルメルト首相を描いたプラカードを振るのは大変結構であるが、ヒズボラのハッサン・ナスララ書記長の顔もあったら、なおさらよかったであろう。
進歩的事例
とにかく、左翼によって言いふらされた一般概念は、最近のレバノンの歴史を精読することの代わりにはならない。現在の危機の起源は、ブッシュやオルメルト、さらにヒズボラよりずっと前にさかのぼる。
1948年のイスラエルの建国から1967年まで、レバノンは平和条約を結ばなくてもイスラエルとの国境で紛争を起こすことはなかった。しかしながら、シリアは、6日戦争で敗北すると、ゴラン高原を取り戻す手段として、イスラエルとの直接の軍事衝突を避け、そのためにレバノンをその代りに使うようにした。
多くの新興の第三世界諸国と同じように、特徴としてレバノンは宗派による多くの違いを持っていた。シリアは、それをもてあそぶことに成功した。シリアがこれらの対立を利用する理想的な方法は、1970年のヨルダン軍との対立後、復讐に燃えるレバノン人とパレスチナ人に武器を与え、パレスチナ人の戦士をヨルダンからレバノンに運ぶことであった。
一方、エジプトのナセル大統領は1969年、シリアと同盟を結び、同じようにレバノンの宗派対立を利用して、レバノン政府にいわゆる「カイロ協定」を押し付けた。その協定の条件は、レバノンのイスラエルとの国境をパレスチナ民兵の管理に置くというものであった。このようにして、レバノンとその領土主権の原則は最初の痛手を被った。
レバノン国家の弱さと戦闘的なレバノン人とパレスチナ人への対処の失敗は、悲惨な結果をもたらした。直接的あるいは間接的にもたらされた結果は、国家を改革したり、その機能をよくしようという圧力ではなく、まったくの破壊であった。
歴史的記録が明らかにしているように、第1次内戦である1975年から1976年までのレバノン人がいう「2年戦争」が起きるまで、事態は悪化した。ついで、シリア軍、パレスチナ人とレバノン人の民兵がベイルートを支配した。一方、それらの民兵と準軍事的な組織が南部国境とベッカー高原を支配し、1982年にイスラエルが侵入するまで続いた。
もちろん進歩的な人々は、レバノンの住民の生活を悪化させ、その経済を破壊し、宗派関係の構成を引き裂いた、そのような侵入を支持しない。しかし、イスラエルの介入よりずっと前に、近隣の準全体主義政権によって画策されたレバノン国家の崩壊も同じように厳しく非難すべきである。
レバノンを守ることがなぜ「進歩的」なのか。第一に、17の異なる宗派が共存するという実験が比較的うまく行っていたからである。確かに、マロン派キリスト教徒が政府を支配していたが、イスラム教徒も非イスラム教徒も、国政の重要なことにも小さなことにも実効的な拒否権を行使していた。
第二に、レバノンは次第に異なる地域社会、地域の間の違いを克服しつつあった。レバノンは、中東で最大の中産階級を有し、そのダイナミックな経済は、ベイルートからずっと離れた地域でも成長が続いていた。
第三に、欠陥はいろいろあったにしろ、レバノンの議会制度はアラブ世界で匹敵するものがなかった。レバノンが同時に、比類ない表現の自由を獲得し、新聞・雑誌が増え続け、独自の作品や翻訳作品を生み出す出版部門が盛んになったのはいうまでもない。ベイルートはアラブ世界の印刷所になった。1975年から1976年の内戦直前には労働組合と政党もまた大幅な自由を享受し、共産党を含むほとんどの左翼運動が合法化された。
戦争前の最後の選挙の年である1972年、共産党の書記長が議会選挙に立候補し、バース党とナセル主義者(レバノンを解体し、汎アラブ同盟の創設を訴えた)も当選した。レバノンにおける女性の地位は、他のアラブ世界のどこよりもずっとよかった。
後退の選択
左翼の人たちは、中東におけるそのようなモデルの崩壊を悲しむべきであった。しかし、そうはせずに戦争を支持し、親西側とみられた「反動的」宗派に反対し、米国の政策に反対する「進歩的」宗派を支持した。言うまでもなく、レバノンの破壊はパレスチナ人に何の恩恵をもたらさず、レバノンをもうひとつのパレスチナにする恐れをもたらしただけであった。当時始まったこの脅威は、今も残る。
1979年のイスラム革命で、米国−イスラエルの影響に対する「抵抗」の最前線でイランがソ連にとって代わるまで、そのような恐ろしい状況は続いた。またしても左翼は、ホメイニ師のイデオロギーの反動的性質、女性不信(misogyny)、農業改革への敵意、進歩的といわれそうなどんなものへの敵意にほとんど注意を払わなかった。
レバノンでは、ホメイニの思想とイスラエルの侵入が組み合わさって、ヒズボラを生んだ。ヒズボラは当初、宗教的少数派のるつぼとして始まった国で、「(シーア派の)イスラム共和国」の創設を訴えた。
ヒズボラについて左翼がしばしば無視した他の重要な事実がある。初めのころ、ヒズボラのベッカー高原のメンバーは、イランの「革命防衛隊」と一緒になっt、少女がひざをみせていたり、顔をベールで覆っていなかったりすると、足に酸をかけていた。
ヒズボラともうひとつの主要なシーア派であるアマルは彼らの間で、イスラエルへの抵抗を独占し、抵抗をシリアとイランに結びつけるために、いく人かの共産主義者と知識人を殺した。
一方、ヒズボラはベイルート南部郊外のキリスト教徒を熱心に「浄化」し、その地区を拠点に変えた。ヒズボラはまた、西側の市民を拉致し始め、イランに米国との取引材料として提供した。ヒズボラは国家外の武装勢力としてとどまり、国家が成立するのを妨げた。
イスラエルが2000年にレバノンから撤兵すると、ヒズボラはその「抵抗」を続け、そうすることで非レバノン人の利益に奉仕した。そして、すべての政治進歩へのカギである国家と、すべての民主的進歩へのカギとなる国民的合意を破壊した。
このすべてのどこに進歩があるのか。もしカール・マルクスが、彼の信奉者がイランの宗教指導者の衣装を着たのを知ったなら、草葉の陰で嘆いているであろう(he would be turning in his grave)。
*ハゼム・サギエフ ロンドンのアラビア語日刊紙アルハヤトの上級評論員。
本稿は独立オンライン雑誌www.opendemocracy.netにクリエイティブ・コモンのライセンスのもとで発表された。
原文
http://www.opendemocracy.net/conflict-middle_east_politics/europe_left_3815.jsp
(翻訳 鳥居英晴)
|















