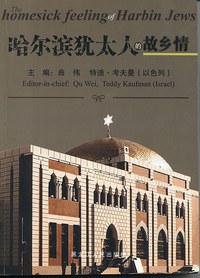・読者登録
・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル
・コラム
・みる・よむ・きく
・インタビュー
・解説
・こぼれ話
特集
・人権/反差別/司法
・政治
・国際
・市民活動
・反戦・平和
・アジア
・みる・よむ・きく
・欧州
・中東
・入管
・核・原子力
・環境
・文化
・イスラエル/パレスチナ
・難民
提携・契約メディア
・AIニュース


・司法
・マニラ新聞

・TUP速報



・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus
・星日報
Time Line
・2026年01月26日
・2026年01月25日
・2026年01月24日
・2026年01月23日
・2026年01月22日
・2026年01月19日
・2026年01月17日
・2026年01月16日
・2026年01月12日
・2026年01月11日
|
|
2007年10月10日17時38分掲載
無料記事
印刷用
日中・広報文化交流最前線
中国におけるユダヤ人の歴史・1 井出敬二(前在中国日本大使館広報文化センター長)
中国国内で研究・紹介が始まった在中国ユダヤ人の近現代史
〜そのインプリケーション〜(その1)
筆者は2007年7月末日、北京勤務を終えて日本に帰国した。北京の日本大使館広報文化センターでは約3年5ヶ月の勤務であったが、その間の経験などを基にして、「日本の対中パブリック・ディプロマシー」という文章を書き、それが9月に出版された『パブリック・ディプロマシ──「世論の時代」の外交戦略』(PHP)という本の一章として収録された。このウェブサイトで書いた問題意識も多く含まれているので、ご参照頂ければ幸甚である。
●中国の対ユダヤ人パブリック・ディプロマシー
さて、この『パブリック・ディプロマシーー「世論の時代」の外交戦略』は、金子将史氏(PHP総合研究所主任研究員)と北野充氏(在米国日本大使館公使、広報文化センター長)が共同編者であり、合計6名の研究者、ジャーナリスト、官僚などが分担してパブリック・ディプロマシーについて様々な角度から論じている。
マイケル・ユー氏(韓国生まれで現在米国で活躍するジャーナリスト)は、「中国の対米パブリック・ディプロマシー」という章を執筆しているが、その中で、近年、中国では、近代中国国内におけるユダヤ人の歴史が紹介され始めており、その事は中国による対ユダヤ人パブリック・ディプロマシーの一環であるとの見方を述べている。
マイケル・ユー氏の記述を一部紹介すると、イスラエルのオルメルト首相について、その祖父はハルビンにいたユダヤ人であり、祖父の亡骸も安置されているハルビンのユダヤ人墓地が最近改修されたことも、オルメルト首相を含めユダヤ人社会に感銘を与えるものであっただろうと記している。(このハルビンのユダヤ人墓地は、アジアにおける最大面積を誇るユダヤ人墓地の由。オルメルト氏もハルビンを近年訪れている。)マイケル・ユー氏はまた、近年、中国国内で「中国のユダヤ人」「ハルビンのユダヤ人」「天津のユダヤ人」といった写真集が続々出版されている状況も紹介している。
●中国で入手できる在中国ユダヤ人の近現代史についての書籍
筆者は本年夏にハルビンと上海(両都市とも、戦前・戦中、ユダヤ人が多く居住したことで知られる。)を訪問する機会があり、その際、両都市におけるユダヤ人の足跡を辿り、「ハルビンのユダヤ人(犹太人在哈尓浜)」「上海のユダヤ人(犹太人在上海)」という写真集を購入した。(前者の写真集は2004年9月初版、2006年6月増訂版、285ページ、社会科学文献出版社刊;後者の写真集は1995年11月初版、90ページ、上海画報出版社刊。)
2004年8月にハルビンで、「ハルビンにおけるユダヤ人の歴史文化に関する国際セミナー」という国際会議が開催され、多くの国(注)から政府、研究機関、友好団体等の関係者が参加している。その際発表された論文集(「ハルビンのユダヤ人の故郷を思う情(哈尓浜犹太人的故郷情)」507ページ、2005年刊、黒竜江人民出版社刊)も単行本として出版されている。(注:同セミナーには、中国、イスラエル以外に、米国、オーストラリア、カナダ、フランス、英国、ロシアから参加者がいたが、日本からの参加はあったとは書いてない。)
中国におけるユダヤ人の歴史は、紀元前の漢代にさかのぼるという説もある。8世紀以降、開封(北宋時代は首都として繁栄した)には、ユダヤ人が来訪し、ユダヤ人コミュニティーもあり、明代に入っても5千人ものユダヤ人が開封にいたという。この点については「Legend of the Chinese Jews of Kaifeng」(Xu Xin著)が詳しい。
中国におけるユダヤ人の歴史は、中国においてどのように紹介されているのだろうか?中国で入手した上記の図書などに拠りながら、以下の通り紹介したい。
●ハルビンと上海のユダヤ人
近代においてユダヤ人の中国への流入には三つの波がある。第一は、清が19世紀後半から外国人商人の活動を認めるようになって来たユダヤ人商人、第二は、19世紀末以降、反ユダヤ主義や、革命、内戦から逃れてきたロシアのユダヤ人達、第三は、ナチの迫害から逃れてきたユダヤ人達である。1940年頃には、約4,5万人のユダヤ人が中国国内にいたとの試算がある(上海ユダヤ研究センター潘光主任の試算)。
ハルビンでは19世紀末からロシアからのユダヤ人の流入が始まり、戦前・戦中の一時は2万人ものユダヤ人が住んでいたと言われる。ハルビンにおけるユダヤ人コミュニティーは、1962年まで存在したとされる。ハルビンには戦前・戦中、ユダヤ人ビジネスマンが経営する数多くの企業(船舶輸送、毛皮加工、石炭、印刷、食品(大豆、チョコレート等)、飲食(レストラン、カフェ経営)、医薬品、ホテル、金融(銀行、証券取引))、4つのシナゴーグ、2つのユダヤ人学校、音楽学校、芸術学校、映画館、病院、養老院、障害者施設などがあった。ユダヤ人の医者、歯医者、音楽家も活躍していた。(この部分は、「ハルビンのユダヤ人」に掲載されているイスラエル・中国友好協会カウフマン会長の文章等に拠る。)
黒竜江省社会科学院は2000年4月にハルビン・ユダヤ研究センターを設置した。2002年には「ハルビンのユダヤ人」という写真展が開催された。黒竜江省は2003年に、「ハルビンのユダヤ人の歴史と文化」を、省として学術研究の一つの分野と認定した。
黒竜江省の官民関係者達は、ハルビンのユダヤ人達が、経済、文化の発展に貢献したと賞賛している。またハルビンの土地が、歴史的にユダヤ人の権利と利益、文化を一貫して守ってきたと主張する。
中国国内最大のシナゴーグもハルビンにあり、その建物は戦後は別の用途に使われていたが、2004年以降、歴史記念館となり、一般市民に開放されている。地元の新聞は、中国で唯一のユダヤ歴史記念館と報じている。黒竜江省およびハルビン市政府関係者によれば、現地政府はユダヤ人に関連する施設等の保存に努力しており、元シナゴーグの建物を歴史記念館に改装するために2千万人民元以上を投入した由。筆者もハルビンのユダヤ歴史記念館を見学してきたが、20世紀初頭から旧満州国時代を通じて、ユダヤ人がどのように暮らしてきたかが分かる写真が展示されていた。
中国国内において旧満州国時代を紹介する展示で、市民の日常生活を伺い知ることができる写真は決して多くないが、この写真からは、ユダヤ人達がハルビンで経済活動、文化活動(音楽会など)など、(多かれ少なかれ)通常の生活をしていた様子が示されていた。この博物館の中には、イスラエル大使館の立て看板があり、イスラエルと中国との友好関係増進を訴える内容の展示があった。いわば、歴史的施設において、イスラエル大使館が対中パブリック・ディプロマシーを展開しているとも言える。
ハルビン市では今後更に他のシナゴーグやユダヤ人中学校、ユダヤ人商店街の再建計画もある由。
上海では、ユダヤの富豪サッスーン家ゆかりの建物(ホテルなど)が多く残っている。筆者は上海のシナゴーグ跡をいくつか訪問したが、その一つは建物が改装中であり、近い将来歴史記念館(博物館)として一般市民に開放される予定とのことであった(写真参照)。とすれば、中国で二番目のユダヤ歴史記念館となろう。またユダヤ人達が戦争中に暮らしていた公園には、その旨の標識がたてられており、アメリカから来たユダヤ人学生達も見学していた。
筆者が、上海市内で、かってユダヤ人達が居住していた地区をウロウロしていたのを見た親切な地元の中国人は、いろいろと案内をしてくれたのだが、文化大革命時代の破壊を免れたユダヤ人の店(ユダヤ語で書かれた看板もかすかに見えた)も教えてくれたりした。(続く)
(本稿中の意見は筆者の個人的意見であり、筆者の所属する組織の意見を代表するものではない。)
|
転載について
日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。
|
|
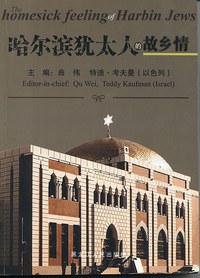
図書「ハルビンのユダヤ人の故郷を思う情」の表紙。建物は、ハルビンのかってのユダヤ教会(シナゴーグ)。現在は歴史記念館として一般公開されている。

上海のかってのシナゴーグの建物の前での筆者(右)。現在修復中で、近い将来、歴史記念館となる由。


|