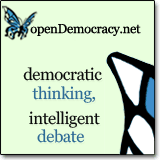 【openDemocracy特約】2008年3月のラサなどで、チベット人の抗議活動が急にエスカレートすると、中国はチベットに対する主権(sovereignty)を改めて強く主張する言辞を用いる一方、チベット人は自決権(the right to self-determination)の主張で反論した。こうした両者の立場は、正当性を立証するための歴史的な参考文献と事実が決定的に依存している。だが、歴史はどちらの側に対しても、どこまで支持を与えるであろうか。
【openDemocracy特約】2008年3月のラサなどで、チベット人の抗議活動が急にエスカレートすると、中国はチベットに対する主権(sovereignty)を改めて強く主張する言辞を用いる一方、チベット人は自決権(the right to self-determination)の主張で反論した。こうした両者の立場は、正当性を立証するための歴史的な参考文献と事実が決定的に依存している。だが、歴史はどちらの側に対しても、どこまで支持を与えるであろうか。
この問題へのアプローチのひとつの方法は、チベットめぐる現代の政治的主張を、中国とチベットによる主権という概念の使用を考慮に入れて吟味することである。そうした読み解きは、両者の政治的主張を複雑化すると言われるかもしれない。たとえば、20世紀初め、チベット人は中国国内の内戦に乗じて、中国人の役人と軍隊を追い出して、彼らの国を事実上(de facto )の独立国にした。そうした状況は、1913年から1949年まで続いた。
しかし、この期間にチベットは独立国家として広い承認を得ることはできなかった。政治的支配権(political supremacy)という中国の法律上(de jure)の主張は疑問を持たれなかった。この意味において、中国はチベットの領有について歴史的、法律的に正当な主張を保持した。
けれども、中国のチベットに対する政治的支配は絶対的なものではなかった。チベットは中国にとって、特別の場所を占めていた。中国の皇帝は仏教徒であったことが多く、仏教徒のモンゴル人をなだめるうえで、チベットのラマは役に立つ同盟者であった。その関係は、檀徒と僧侶の関係に似ていた。それは、宗教的、象徴的、政治的な内容をもったものであり、主権とか独立(independence)といった絶対的な用語とは異質なものであった。( Gray Tuttle, Tibetan Buddhists in the Making of Modern China参照)
絶対主権という欧州の概念を中国が使用することは、この関係に特別の負担を与えた。それはそれ自身、二つの要素の産物であった。つまり、20世紀初頭における中国の民族主義の台頭と、欧州の語彙を使って中国とチベットの関係を名づける英国領インドの試みであった。
この意味において、中国のチベット支配は、二つの異なった帝国の軌跡(ひとつは中国、もうひとつは西洋)を通じて理解しえる。中華人民共和国は、チベットに対する支配を合法化するために、歴史的な帝国のつながりに主に焦点を当てる一方で、主権という概念を用いている。主権という近代的概念は、帝国主義と非植民地化を通じた欧州の普遍化の産物である。そのことは、近代チベットを「記述」するうえで、西洋の帝国主義者の軌跡の重要性を示している。
重要な変容
チベット人の国民性・民族性(nationality/ethnicity)は非常に早い段階から、漢族、回族(すべてのイスラム教徒に用いられる)、満洲族、モンゴル族の範疇とともに、近代中国人の国民意識の中核にあった。一方、西洋(欧州、米国、この文脈では日本の)帝国主義の衝撃と、「偉大な連続した文明」としての中国という自覚が組み合わさって、中国の民族主義は仮想の集合性に対するどのような挑戦に対しても自意識過剰になった。
こうして、チベット人は、近代中国の民族主義、1950年の軍事的「解放」と1951年の「17ヶ条協定」より以前の国民国家の不可分の部分になった。もっと広く言うと、今日の中国政権は、支配を合法化する主要な手段として民族主義を利用している。資本主義的な経済の運営に専制的な支配を組み合わせているので、チベットであれどこであれ、民族の民族主義(ethno-nationalism)が政治的形態をとることについては、過度の猜疑心を持たざるを得ない。
チベットにおける英帝国主義の活動も、中国のチベットに対する態度の変容で重要な役割をはたした。特に、1903年から1904年のヤングハズバンド大佐の率いる軍の侵入により、中国のエリートはヒマラヤを越えた南からの敵対的な勢力への脆弱性を認識した。20世紀前半での英帝国の政策の最も重要な側面は、「中国の宗主権(suzerainty)−チベットの自治権(autonomy)」という方式であった。だが、チベットの政治的地位につてあいまいさを助長するうえで、この計算された戦略的偽善は長く続くものではなかった。
1940年代後半はこの点に関して、重要な時期であった。英国は1947年にインドから撤退した。内戦での共産主義の勝利は1949年以降、中国で安定した政府が出現したことを意味した。同時に、そうして出来事は、「中国の宗主権―チベットの自治権」の方式の文脈が変容させられたということを意味した。20世紀の始まりから中国はチベットへの主権を維持していたが、いまや、この主張を実行し、チベットを軍事的に「解放する」(中国はそう見る)立場にいた。インドにおける帝国の終わりとともに、英国はチベットを戦略的に重要なものとは見なさなくなった。
独立の幕開けにあったインドは、チベット問題を地域の英帝国主義の遺物と見なす反帝国主義の民族主義に駆り立てられていた。その結果、インドが画定した国境と考えたものは、実際には英領インドとチベットの間のシムラ協定(訳注)の産物であっと認識することなく、インドは中国のチベット支配を受け入れてしまった。(仮調印後、中国はそれを不平等条約だとして拒否した)。こうして、インドがチベットを中国の一部であると認めたことで、両国間の国境問題に道を開いた。
1940年代後半になって、チベット人は遅ればせながら独立した地位の確認のために国際的な支持を求めようとしたが、失敗に終わった。中華人民共和国はチベットを自治区ではあるが、中国の不可分の一部として地政学的に記述することを、欧州の憲法の武器庫の中から最も強力な武器のひとつ、つまり主権という概念でもって完成させた。チベットの地政学的なアイデンティティは「宗主権―自治権」から「主権―自治権」に変換された。主権という概念がその利益と野望に最も役に立つことを発見したのはチベットではなく、中国であった。
歴史の利用
「チベット問題」が主権と自治権という競合する概念によって、どのように組み立てられていったのかをみてみると、ポスト植民地世界で政治的問題が解決困難なのは、長年の歴史的憎悪や「本質的な」文化的違い以外の要素によるものであることがはっきりする。主権や民族主義という概念はもともと西洋のものであったが、非西洋の関係者は、それを彼ら自身の政治共同体の観念を変容するために流用してきた。(この議論のさらなる発展のためには、わたしの著書Geopolitical Exotica: Tibet in Western Imaginationを参照のこと)
この事業では、「伝統」は近代的国家である状態(statehood)の主張を支持する方便として利用される。非植民地化の重要な時期に敗れたチベット人のような人々は、現存する支配国家が分裂するか、他の大国が既成国家からの分離を支持しない限り、分離した国民国家として認められるように、納得させる主張を唱えるのは困難になる。
チベットの場合、こうした条件のどちらも可能性はない。このことは、ダライ・ラマの指導のもとにある海外にいるチベット人は、術策の余地がほとんどないということになる。彼らの苦境の一因は、中国が主権という語彙を流用する中で、西側は近代チベットの帝国的な記述を通して、中国の同盟者であったということである。
絶対的なのもの限界
チベット問題を歴史の文脈にあてはめることは、現代の政治的議論の背景の説明を助けるうえで重要である。歴史というものが現在の立場を支持するためのもの以上であるなら、前向きのとなる要素を示すかもしれない。たとえば、英帝国が介入する以前は、中国とチベットの関係は相互利益のために便宜を図ることが多かった。チベット人は中国からの政治的圧力を通常、感じなかったし、(それを「独立」と呼ぶことなしに)かなりの自由があった。一方、中国は(その地区に多く投資する必要なしに)全体的な政治的支配を認めた。
ある時には、国際的なシステムと個々の国家は、主権という絶対的な概念は、ためになるより害を与える可能性があるということを認めなければならないであろう。これはまた、中国内におけるチベットのために、人間的で効果的な解決策への道を開くであろう。当分の間は、中国政府が次のように自覚することが望まれる。意見の相違と抗議を許容する体制は永続的な解決策を産み出しえるが、その市民に永久に疑いを抱いたままの体制はそうした解決策を産み出すことはできない。
*ディベシ・アナンド 英国のウエストミニスター大学民主主義研究センター准教授。ポスト植民地の国際研究、中印関係、中国、チベット、インドを研究。
訳注 <A href="http://www.claudearpi.net/maintenance/uploaded_pics/1914ConventionbetweenGreatBritainChinaandTibet.pdf" target="_blank">シムラ条約</A> 1914年に英国とチベットの間で調印された。「チベット本土は中国を宗主とする自治国家であること、中国のアンバンはその階級と地位にふさわしい軍隊の護衛とともにラサヘ戻ること、中国と英国はチベットの政治に何ら介入しないことなどが三者によって賛同されたが、チベット国境の問題で見解の相違が大きく、協定不可能に」(Wikiwiki Tibetan Lab) アンバンとは中国からの大使のような役職。注記において、チベットは中国領土の一部であると理解されている。英全権代表ヘンリー・マクマホンは、インド領の東部国境線を北上させる条項をチベットと締結。この国境線(マクマホンライン)が元で1950年代後半、中印国境紛争が表面化した。
【宗主権】 他国の主権を従属的に制限する権能。国家が独立する過程で、本国が独立する国に対してもつ場合が多い。
【主権】 (1)国家の統治権。他国の意思に左右されず、自らの意思で国民および領土を統治する権利。領土・国民とともに国家の三要素をなす。 (2)国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利。
「広辞苑」より。
本稿は独立オンライン雑誌www.opendemocracy.netにクリエイティブ・コモンのライセンスのもとで発表された。 .
<A href="http://www.opendemocracy.net/article/china/globalisation/tibet_china_clash" target="_blank">原文</A>
(翻訳 鳥居英晴)
|















