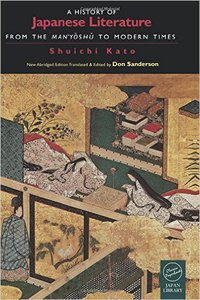・読者登録
・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル
・コラム
・みる・よむ・きく
・インタビュー
・解説
・こぼれ話
特集
・アジア
・農と食
・人権/反差別/司法
・国際
・イスラエル/パレスチナ
・入管
・地域
・文化
・欧州
・市民活動
・検証・メディア
・核・原子力
・環境
・難民
・中東
提携・契約メディア
・AIニュース


・司法
・マニラ新聞

・TUP速報



・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus
・星日報
Time Line
・2025年04月04日
・2025年04月01日
・2025年03月31日
・2025年03月30日
・2025年03月29日
・2025年03月28日
・2025年03月27日
・2025年03月26日
・2025年03月23日
・2025年03月22日
|
|
2017年02月26日10時22分掲載
無料記事
印刷用
みる・よむ・きく
加藤周一著 「日本文学史序説」
外国人の友達ができる、ということは日本について語る機会が増える、ということで、しばしばその都度、自分の日本文化に対する無知を自覚させられることになりえます。外国人だから適当に説明してもわからないだろう・・・と思っていたら大きな間違いで、相当深く日本文化を研究している外国人も少なくありません。戦後を代表する評論家の一人、加藤周一は外国文学に深い知識を持ちながら、同時に日本文学をその黎明から研究し、その研究成果を「日本文学史序説」という二冊組の本で発表しています。この本は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、中国語、ルーマニア語などに翻訳されたとされます。それだけ外国の研究者に必要とされる理由は日本文学の黎明である8世紀から現代まで、縦に文学史を語り、そこに加藤独特の知見を組み入れたからに他なりません。
加藤周一について筆者が初めて知ったのは高校時代に国語の教師から加藤の代表作の1つである評論「雑種文化」について聞いたことでした。「雑種文化」の骨子は〜高校時代に読んだ時の記憶によりますが〜日本文化にはその起源より多様な要素が詰め込まれているということでした。加藤は「古事記」などの神話も、日本の土着の神話がアジアの南方型、北方型の神話の型と融合され、創り出されていったのではないか、と推測しています。実際に外国の神話と同じパターンが随所にあると「日本文学史序説」で加藤は指摘しています。
「素材のなかでももっとも古い部分、すなわち神話の断片の構造は、日本に固有のものではない。たとえば太陽神(アマテラス)の広い分布は、いうまでもないし、その子孫の神(ニニギノミコト)が天上から山頂へ降臨するという型の話も、広く北方アジアに行われている。朝鮮の恒雄が太白山の頂に降りたのも、その一例である。ニニギノミコトがコノハナノサクヤヒメと婚し、イワナガヒメを斥けたために、その後の人の命が岩のように長くありえず、木の花のように短くなったという説話は、南方型(「バナナ型神話」)とされる。アメノウズメノミコトに代表されるシャーマン的要素は、北方型であり、海幸彦・山幸彦の挿話に典型的な海に関連する伝説の多くは、南方型である。そういう神話の伝わってきた径路と時期はあきらかではない。しかしいずれにしても、『記』・『紀』の素材が集められたとき、すでに土着の信仰・伝説と化していた話の内容が、北方型・南方型を含む複雑な合成体であったらしい、ということは、確かであろう。素材に独特のものはなかった。しかし多くの地方的な素材を総合して、一種の神話体系をつくりだしたということに、日本の古代の特徴があった」
もともと無文字社会だった時の日本の支配階級が中国の文字を導入して書くことを始めたという歴史があります。現在、英語が学校により初期から組み込まれようとしていますが、これが何をもたらすのか、そのヒントも日本の歴史の中にあるのではないでしょうか。日本の歴史は漢字という中国言語を用いながらも、日本人の感性をよりストレートに表現できるように発展してきましたが、その一方で漢字を廃止することなく、漢字によって中国語の概念や論理構造を利用して近代の黎明期に西洋文明を素早く吸収することもできました。もし、漢字を捨て去って、ハングルやベトナム語のようにひらがなとカタカナだけにしていたなら、日本も近代の初期に大衆が西洋文明を理解するのに時間を要したかもしれません。
(以下は「日本文学史序説」から)
「『万葉集』には、女流歌人が多い。おそらく抒情詩の作者にこれほど女の多かった時代は、古今東西に例が少ないだろう。しかも『万葉集』の閨秀は、傑作を生みだした。けだし日本の女流文学は、突然平安時代の女房文学にはじまったのではない。すでに、『万葉集』の時代からこの国の文学に女の演じてきた役割は大きかったのであり、女流作家が消えていったのは、13世紀以来の武士支配階級の倫理、殊に儒教イデオロギーを借りて強化された男女差別観の徹底による」
「少なくとも7世紀以後19世紀まで、日本文学の言語には2つがあった。日本語の文学と中国語の詩文である。たとえば『万葉集』と『懐風藻』、『古今集』と「文華秀麗集』。ここで日本人の感情生活が、外国語の歌に、はるかに豊かに、はるかに微妙にあらわれていたことは、いうまでもない。・・・・二か国語併用の歴史は、当然、漢文脈とその語彙の日本語文への影響を生み、また逆に日本語の影響をうけた日本人独特の漢文を生んだ。前者の例は、すでに『今昔物語』にみられるし、後者の例は『明月記』にみられる。殊に日本文のなかに、漢文の影響の強い文体と、口語にちかく漢文の影響の少ない文体とを生じたことは、日本語文学の表現力の拡大に測り知ることのできない貢献をしたといえる。明治以後の日本社会が西洋の概念を輸入する必要に迫られたときに、長い間に日本語のなかに吸収消化されていた漢語が、どれほど大きな役割を果たしたかは、今さらいうまでもないだろう」
「知識人の2つの型を代表していたのは、衆目のみるところ、菅原道真と紀貫之である。官界に地位を得るための文芸(いわば表芸)は、シナ語の詩文であったから、道真は当然シナ語で書いたし、また書かざるをえなかった。不遇の貴族、貫之は、おそらく官界に野心がなく、日本語の新しい表記法(かな)を利用して、母国語の抒情詩(裏芸)に専念することをためらわなかった。」
「日本文学の歴史は、長かったばかりではない。その発展の型に著しい特徴があった。一時代に有力となった文学的表現形式は、次の時代にうけつがれ、新しい形式により置き換えられるということがなかった・・・(中略)・・・このような歴史的発展の型は、当然次のことを意味するだろう。古いものが失われないのであるから、日本文学の全体に統一性(歴史的一貫性)が著しい。と同時に新しいものが付加されていくのであるから、時代が下れば下るほど、表現形式の、あるいは美的価値の多様性がめだつ。」
|
転載について
日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。
|
|
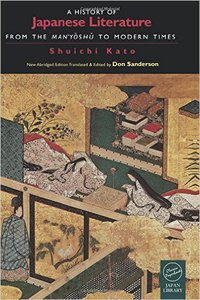
加藤周一著「日本文学史序説」の翻訳版





|