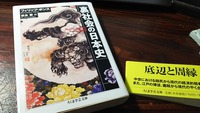・読者登録
・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル
・コラム
・みる・よむ・きく
・インタビュー
・解説
・こぼれ話
特集
・アジア
・農と食
・人権/反差別/司法
・国際
・イスラエル/パレスチナ
・入管
・地域
・文化
・欧州
・市民活動
・検証・メディア
・核・原子力
・環境
・難民
・中東
提携・契約メディア
・AIニュース


・司法
・マニラ新聞

・TUP速報



・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus
・星日報
Time Line
・2025年04月01日
・2025年03月31日
・2025年03月30日
・2025年03月29日
・2025年03月28日
・2025年03月27日
・2025年03月26日
・2025年03月23日
・2025年03月22日
・2025年03月21日
|
|
2019年04月30日20時06分掲載
無料記事
印刷用
みる・よむ・きく
フィリップ・ポンス著 「裏社会の日本史」(ちくま学芸文庫)
フィリップ・ポンス著「裏社会の日本史」は長い間、読もうと思いながら、ようやく買って手にしたのは2〜3週間前のことだ。躊躇した理由はかなりなボリュームのある本であることと、日本社会の暗部を研究して描いた社会学的な本であることだ。そこには貧困者やホームレス、あるいはやくざやテキヤといった稼業の人々のことが描かれているらしいのである。
「本書では『極道』と貧苦の領域に関する報告書を作成するにとどまらず、歴史学から現地探索に至るまで複数のアプローチを組み合わせ、固有の行動規範や道徳、歴史を有する陰の社会システム作成の過程を捉えること、要するに日本語の表現を借りれば『雑草の文化』とも呼びうるものの諸側面について検討することを試みた」と序章にある。
ポンス氏の記述を読んでいて加藤周一の「日本文学史序説」と通じるものを感じる。日本の社会がどのように形成されてきたか、その歴史と社会学的な分析を交えて、かなり長い射程で検証していることだ。フィリップ・ポンス氏はもともと研究員として来日した後、ルモンド紙の東京支局長になった人物とのことだが、日本では考えられない職業的な発展ということも興味深い。日本では基本的に新聞社内で移動していくだけだろうからだ。だから、こういう研究者を記者にして、支局長に登用するというフランスのメディアも面白い。
「16世紀の後半まで、賤民は、新たに耕地を切り拓いたり、廃田を耕したりすることで、農民になる希望を持つことができた。しかし、豊臣秀吉が1582年から91年まで行った検地によって、農民は土地に縛り付けられ、実際に全ての耕作可能な土地は細分化された。以来、列島の北の蝦夷地を除いては、新参者が農民になることは殆ど不可能となった」
「都市の下層民、ことに住居も職もない貧民の群れの監視と管理のために、非人の身分が公式に制定されたのは17世紀初めである。彼らの最大の罪は、寄る辺なく、物乞いするほか生活の糧を得られないことであった。非人は、本質的には都市の現象である。非人の共同体は依然として浮動的かつ不安定であり、社会的落伍者など、些細な盗みを働いた不良少年や、乞食、障害者などで構成されていた」
「(炭鉱の)生活条件は劣悪を極め、炭鉱の家族たちには寝具さえなかった。寮には茣蓙さえなかった。長らく北海道では、炭鉱労働者は囚人が務めたが、彼らは『タコ部屋』と呼ばれる小部屋に住んでいた。自分の足を貪って死んでいく囚われのタコさながら、生きて炭鉱を後にすることはできなかったのだ。日本の炭鉱労働者の3分の1を朝鮮人が占めていた」
「被差別部落が多く存在する奈良に生まれた小説家、住井すゑ(1902−1997)は、幼少時から差別にまつわる体験を重ねてきた。彼女は、二十世紀に入って、日本近代の被差別民の状況に関する鮮烈な証言を行った。地主の娘だが、幾分反抗的な気質の持ち主であった住井は、1920年代に夫が参加していたアナーキズム運動に身を投じる。彼女は人一倍、社会的差別に敏感だった」
「長らくテキヤの世界では、客を集め、祭りの雰囲気を作り出すことができるために本当のプロと見なされていた口上師(コロビシ)と、口上なしにただ物を売る商人(ジンバイシ)との間に、截然たる区別があった。コロビシだけが、寺社の境内に露店を出す特権に浴することができた。コロビシはまた移動する権利を持っており、料金を納めることにより、自分が所属する組とは別の区域で活動を行う権利があった」
「1990年代後半になると事情は変わってくるようである。商法改正後の10年間で、第一線の20社ばかりの企業が、動く金が次第に高額になるばかりの一連のスキャンダルで総会屋との関係を告訴された。1992年10月に、大手スーパーチェーンのイトーヨーカ堂グループが総会屋に暴力団員を雇っていたことが発覚し、スキャンダルとなった。翌年、国内で40%近くのシェアを持つキリンビールが窮地に陥っていた。調査の結果、キリンビールは10年間で2億円を渡していたことが明らかになった。」
「やくざは、日雇労働者を仕切り、利用し、またスト破りの手下を送り込んだりすることによって、社会の浮動層の『導き手』の役割を果たした。当局の管理をすり抜けるような境界的な社会空間を管理する一種の権力の代理という地位を手にし、やくざは裏の警察の役割を果たしているのであり、日本は、ミシェル・フーコーが権力による『非合法性の植民地化』と呼ぶものの典型例なのである」
「裏社会の日本史」の原題は「日本の悲惨と犯罪」という意味なのだが、上っ面な社会の表のハレの顔ばかりでは見えない日本の深層が描きこまれていて興味深い。
今、元号が変わろうとしているが、天皇に関する言説ばかりになっている中で、日本の身分制度を振り返る言説はほとんど見られない気がする。天皇制はそれだけで生まれてきたものではなかろう。しかし、日本のメディアは歴史的に形成されてきた天皇を頂点とする日本社会のヒエラルキーを見ようとしないことで堅く結束しているようにも思える。だからこそ、どこか浮ついた地に足のつかない言論空間になっているように感じられる。
|
転載について
日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。
|
|
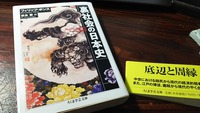
フィリップ・ポンス著 「裏社会の日本史」(ちくま学芸文庫)





|