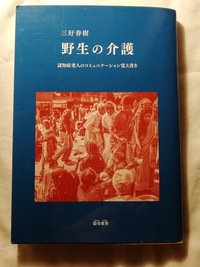・読者登録
・団体購読のご案内
・「編集委員会会員」を募集
橋本勝21世紀風刺絵日記
記事スタイル
・コラム
・みる・よむ・きく
・インタビュー
・解説
・こぼれ話
特集
・農と食
・人権/反差別/司法
・アジア
・国際
・イスラエル/パレスチナ
・入管
・地域
・文化
・欧州
・市民活動
・検証・メディア
・核・原子力
・環境
・難民
・中東
提携・契約メディア
・AIニュース


・司法
・マニラ新聞

・TUP速報



・じゃかるた新聞
・Agence Global
・Japan Focus

・Foreign Policy In Focus
・星日報
Time Line
・2025年04月01日
・2025年03月31日
・2025年03月30日
・2025年03月29日
・2025年03月28日
・2025年03月27日
・2025年03月26日
・2025年03月23日
・2025年03月22日
・2025年03月21日
|
|
2020年12月11日11時53分掲載
無料記事
印刷用
社会
< a care-worker’s note・5> 開かれた介護環境をつくるために~三好春樹「野生の介護」より、認知症高齢者とのコミュニケーションを考える 転石庵茫々
コロナ禍による大量失業者の発生により、介護業界に他業界からの人材流出が、2020年秋ごろから起きるという予想がありましたが、勤務先の介護付き有料老人ホーム周辺では、まだ、実感としては感じられません。この秋から年末にかけて、勤務先にも3人の入職者がありましたが、全員が介護士歴10年以上の技能をともなうベテランで、中高年のベテラン介護士の転職が多いような感じです。
介護職の転職の理由は、①給与の低さ②利用者とのトラブル③職場の人間関係と言われています。給与の低さは、介護保険に依存している介護業界全体が抱える経済構造的問題です。利用者とのトラブル及び職場での人間関係は、他者とのコミュニケーションが基盤になっている介護職特有の転職理由かもしれません。
今回は、高齢者介護の第一歩である高齢者特に認知症高齢者とのよいコミュニケーションのあり方を三好春樹氏の著作である『野生の介護』から考えてみたいと思います。(職場での人間関係については、稿をあらためます。)
著者の三好春樹氏は、1950年の広島生まれ、高校時代に学生運動で退学、どこも勤め先がなく、特別養護老人ホームへ就職。夜勤中に読んでいた文化人類学者レヴィストロースの本でブリコラージュという言葉に出会い、「介護はブリコラージュ」という認識(というか発見ですね)をもち、その認識をもとにした活動で、介護界のカリスマのひとりになった人です。認知症高齢者を異文化という視点で捉えてゆくのが、彼の特徴的な視点です。
ブリコラージュとは、ありあわせのものを素材にして、ものを作ってゆく作業のことです。レヴィストロースは、ものをつくる設計にかかわる思考と実際の作業での柔軟な実行性を合わせて、ブリコラージュと言っています。
タイトルは一目瞭然で、レヴィストロースの代表的な著作である『野生の思考』からきていますが、本書の主テーマは、副題にある通り「認知症高齢者のコミュニケーション」です。
◆<との>コミュニケーション、<からの>コミュニケーション
認知高齢者とのコミュニケーションには、<との>のコミュニケーションと<からの>のコミュニケーションがあるということから始まります。テーマに即すれば、「認知症高齢者とのコミュニケーション」と「認知症高齢者からのコミュニケーション」です。
「認知症高齢者からの」コミュニケーションが理解できなければ、「認知症高齢者との」コミュニケーションは、認知症高齢者に対してこちらからの一方的な視線で行われているだけの、こちらの価値観を押し付けるだけの、いわばフランスの哲学者であるフーコーに倣っていえば、権力関係に基づく関係でしかないということです。
ここから認知症高齢者との交流をといてゆくのが、三好式です。
介護学校で習う一般的なコミュニケーションの第一項目は、<声かけ>です。高齢者には、常に声かけをして、励まし温かい関係を作ってゆきましょう、ということを習います。
その結果、残念ながら、中途半端な理解者が生まれ、無暗に認知症高齢者に声かけをする介護職や福祉関係者が誕生します。
夜勤明けで、引継ぎまで少し時間があり、デイルームで見守りをしていると出勤してきた介護職やケアマネの中には、デイルームで朝食後のぼやっとした時間を過ごしている高齢者ひとりひとりに、非常に熱心に、明るい声で「おはよう!おはよう!」と言って、手を握ったり肩を抱いたりする輩がおります。私はだんだん腹が立ってきて、うるさいから向こうに行け!とあくまでソフトに言うことがあります。こういう輩を「声かけ信者」と名付けてますが、こういう人たちの高齢者との交流は、万事、相手の状況をみない一方的な行動です。
これが<との>の悪例である一方的なコミュニケーションの一例です。声かけ信者は、高齢者<との>交流を充分に行っていると信じているでしょう。なぜなら、彼らは、高齢者に対して、「寂しくかわいそうな孤独な人たち」という一方的な思い込みがあり、ともかく、職業的使命感もあり、植物に水をあげるように声かけをしようという善意に基づいて行動しているからです。この一方的な思い込みからくる行動こそ権力であるのに、です。善意は、正義を味方にしていると勝手に思っているので、ほんとにコワいです。
三好氏によれば、認知症高齢者<からの>コミュニケーションの実例は、徘徊、妄想などの問題行動にあるということです。
一般的な認知症理解では、中核症状(記憶障害、見当識障害、言語障害、実行機能障害、失認、失行)があり、そこから発生する周辺症状BPSD(徘徊、妄想、詐話、暴言、暴力、無為無反応、介護拒否、排泄トラブルなど)が発生すると捉えられ、周辺症状は、問題行動といわれています。
三好氏の考え方は、この問題行動のなかには、認知症高齢者<からの>コミュニケーション(=認知症高齢者各自の独特のコミュニケーション方法)があるという見方です。言い方を変えれば、かれらひとりひとりにとってのそうならざるを得ない行動表現をとったコミュニケーションへの訴えなのです。といっても、もちろん問題行動のすべてに意味があるわけではないことも付け加えてあります。いくら解釈をしても仕方がないこともあります。特に限られた時間のなかでは。
認知症高齢者の行動振る舞いを異文化としてとらえるという野生の介護的視点からすれば、徘徊は、彼らがコミュニケーションをとるためのひとつの文化的方法であり、私たちに対する彼ら独自の私的コミュニケーションの誘いですから、十把ひとからげに、一群の問題行動という枠組みに入れてしまえば、介護する側からの価値観による一方的な決めつけしか残らないことになります。
私には、三好氏のこのコミュニケーション論は、経験的に、たいへん馴染みのあるものであり、納得がゆきます。施設介護の場合(訪問介護でも)、限られた時間と空間で行うことなので、ひとりひとりに付き合っていられないという難点はありますが、認知症高齢者とのコミュニケーションに対する基本的な考え方はこの通りと思います。
また、実際の現場での観察から、ありていに言えば、優秀なベテラン介護職ほど高齢者のもっているその人<からの>独特のコミュニケーションの仕方を把握確認して、そのひと<との>コミュニケーションを始めています。冒頭に書いた勤務先に新しく入職した介護士3人をベテランと称したのは、彼らが新しい職場にいる利用者の皆さんを介護技術を駆使しながら、ゆっくりと観察し、ひとりひとりの<からの>コミュニケーションを確認している姿勢が見られたからです。
<からの>から<との>コミュニケーションに移ってゆくと、次の課題がやってきます。
◆高齢者の<自己決定>から高齢者との<共同決定>へ
介護学校で習うというか介護福祉士試験の常套である、高齢者による「自己決定の原則」という問題です。介護にかかわる何事も高齢者による自己決定を最優先する(少し極端ですが、現在の行政の教科書はこの方向です)、という金科玉条の原則です。
中核症状を発している高齢者に自己決定を要請するというのは、実際には、多くの場合、高齢者自身は自己決定できないために自己決定を要請したひと(=介護職)の自己決定になってしまっています。「老人の自己決定とは、私たち介護職の自己決定であると言ってもいいくらいである。」それ以前に、「声かけ信者」の前では自己決定できる高齢者なんぞはおりません。声かけ信者の善意による行動決定のみが実践されるだけですから。
よくある例として、トイレに行きたがっている認知高齢者がトイレがない方向へ意固地になって向かっている場合どう対応しましょうというのが、あります。このときに介護職としてどう対応するか、です。行政の模範解答は、見守りが前提で、認知高齢者のおもむくままに任せるとなります。トイレに間に合わなくて、尿漏れなどを起こし下半身がびしょびしょになってでもです。声かけ信者は、こっちじゃないよと声掛けして、後は半ば強制的にトイレに連れて行ってしまいます。熱心な声かけ信者ならずとも真夜中など余裕のないときは介護職は失禁したあとの着替えや清掃などの後処理の煩雑さを思えばこうするでしょう。
ここで重要なことは、<からの>を経て<との>のコミュニケーションを形成してきた介護職ならば、少しでも余裕がある場面では「共同決定」が少しはできるようになっているということです。
家に帰りたいという帰宅願望を例にすれば、荷物を整理して抱え帰宅する気になっている認知症高齢者に、頭ごなしに帰宅拒否したりウソをついてその場をやりすごすのでは、家に帰りたいということで示そうとしている、認知症高齢者からのコミュニケーションの中身がわかりません。まして、そのまま居室に押し返してもそれこそ何度でも帰宅するために居室からでてきます。これは、大げさな表現ではなく、夕方から朝まで帰宅願望を訴えに介護が待機しているナースステーションまでくる認知症高齢者は少なからずいます。疲れ切って、おそらく自分でも何をやっているのかわからなくなってしまっても、ふらふらになって私たちのところへやってきます。
やはり、なぜ帰宅したいのか、を訊き、今は帰宅できないけどどうしようかという相談をして、話し合い、今夜の過ごし方について「共同決定」する、のが、お互いのためでもあるわけです。
お互いのため、というのは、とても大切なことです。よく病院と介護施設の違いについての話が出ますが、ひと言で言うと、これは非日常と日常の違いです。病院は、病気をなおすためにある有限的な非日常世界ですが、介護施設は、日常生活を延々と送る世界です。そこには、穏やかな日常が望まれるわけで、できるだけ非日常を避ける空間が介護施設であり、日常のルーティンスケジュールを安全安心に進めることが重要になります。娯楽としての非日常は大切ですが。
三好春樹氏というひとは、介護職ならば北欧ではなくインドに行ってこい!というひとですから、とことん異文化理解を基礎に認知症高齢者介護を行ってゆきます。異文化理解は、理解したい他者を病的な非日常にいるのではなく、ひととして普通の日常世界にいることを前提としてできることではないでしょうか。
ここまで「声かけ」という視点から、認知症高齢者のコミュニケーションの可能性を探ってきましたが、「声掛け」と同じように介護職に要請されることに「傾聴」があります。「傾聴」は、カウンセリングに活用されてきたコミュニケーションの技法で、相手の話に疑問を呈したり、自分の考えを言ったりしないで、聞き役に徹するというものです。
<声かけ>と<傾聴>が同じレベルにあるというのは、「<声かけ>は、<誰からも声をかけてもらえないでいるかわいそうな老人>であり、<傾聴>は、<誰にも話を聞いてもらえないでいるかわいそうな老人>であるという一方的なイメージである。」からと三好氏は指摘します。これも介護の現場でたびたび目にしている風景です。かわいそうな認知症高齢者たちがいるという善意ではあるが過剰な思い込みでいらっしゃるボランテアの方も少なくはありません。かわいそうな認知症高齢者がいるということはありますが、声かけや傾聴等の意図的なかかわりをするのではなく、「周りの人たちとの無意識なかかわりの中に<声かけ>や<傾聴>が自然に存在する日常があればいいのである。」とあり、「それをつくり出すことこそ介護ではないのか。」と介護職に向かってとってどきりとする言葉が投げられます。三好氏の主張に同意して安心して親しんでいると厳しい問いが投げかけられ、三好春樹劇場の単なる観客のままではいられません。
◆<ケースワーク>と<介護>
<声かけ>や<傾聴>が表層的な技術だとすると、「もう少し深層でひととの関わり方やコミュニケーションのあり方」に基づいて作られたコミュニケーションの型を介護のコミュニケーションに適用するということも行われてきています。
代表的な例としてケースワークからの適用があります。ケースワークとは、「社会事業の一方法で、精神的・肉体的・社会的な生活上の問題をかかえる個人や家族に個別的に接し、問題を解決できるように援助すること。ソーシャルケースワークの1種。」(デジタル大辞泉)です。三好氏は、ケースワークと介護の違いを3つ挙げて、ケースワークの技法の介護への無批判での導入に疑問を呈します。
バイステック『ケースワークの原則』の中に、「他の専門職、たとえば、外科や歯科や法律にあっては、人間間の良い相互関係は、サービスの<完全性>のため望ましいものであるが、それはサービスの<本質>にとって必要なものではない」とあり、外科医などが依頼されたサービスをはたし評価されることが本質であるが、ケースワーカーにとっては、「良い関係はその本質にとって必要である。」とあるそうです。即ち、ケースワーカーにとって、相手との良い関係づくりが本質であり、目的でもあるのです。
三好氏は、ここにある専門職(外科医や歯科医、弁護士など)を三大介護技術である、食事、排泄、入浴に置き換え、食事、排泄、入浴などの介護技術がいくら素晴らしくても、それは介護の本質か?と問います。介護の本質といえば、やはり、介護対象者との良い人間関係では、ないでしょうか。さらに言うと、「食事、排泄、入浴を通して<よい関係>に至る方法と、逆に<よい関係>から介護に至る」という双方向を柔軟に行うのが介護というわけです。これが、ケースワークと介護の違いのひとつ目で、ケースワークと違い介護は、食事、排泄、入浴という具体的な世界を持っているということもあらためて指摘されます。
二つ目は、「ケースワークは特別な状態におかれた人を相手にするものだが、介護関係は日常的な生活の中で行われるものだということである。」で、介護は日常生活の中で行われることがここでも強調されます。
三つ目は、「ケースワークはケースワーカーとクライアントのとの1対1で行われるが、介護関係は基本的に1対1ではなくて、他の関係へと変化していく開かれた関係なのだ。閉じてはいけない関係と言ってもいい。」です。孤立して引きこもった高齢者に対して、1対1からの信頼関係をつくるための閉じた期間があったとしても、「関係の喪失から多様で相互的な関係へと至る回復過程の一段階としてのことだ。」となります。
介護が基本的にほかの関係へと開かれた関係というのは、<声かけ><傾聴>で陥りがちであった一方的な関係(権力的関係)から<声かけ><傾聴>を自然に行う環境づくりの提案でいわれている、利用者さん同士も含めた<お互い>の関係の状態でもあるでしょう。
◆外部へ開かれた関係をつくってゆく介護
この本では、ここまでが、この本の「第一章この本を書く問題意識」です。「第二章コミュニケーションは始まっている」では、北海道日高地方の浦河町にある「ぺてるの家」という精神障害者の運動体の活動の紹介。「第三章まず自分とのコミュニケーション」では、認知症高齢者とのコミュニケーションの下手なひととは自分自身とのコミュニケーションができない人ではないかという仮説とその解決について。「第四章コミュニケーションが成立する条件をつくる」では、認知症高齢者とのコミュニケーションが行き詰まったときの気を変えて打開することの重要性とその方法。と第一章の問題意識の展開が続きます。
三好春樹氏の面白さは、<声かけ><傾聴>あるいは<ケースワーク>といった既存の方法を批判的に検討しながら、その方法の底にある真の狙いをもういちど捉えなおし、活気づけるところだと思います。高邁な理想からではなく、実際の現場でのトラブルのシーンから始まり、その解決方法を介護職のポケットの中にある介護職のもっている方法論を組みなおし深めてゆきます。その実践の中では、1対1の中に、あるいは少数のグループの中に閉じられがちな介護関係の作業や人間関係を少し外へと開いてゆく力強さを感じがします。
近親者や身近な方で介護が必要な状態になった方がいて、介護に関わらざるをえなくなったひとから、介護の相談を受けて、まず、僕から話すことは、施設に預けるにしても、近親者で見守るにしても、ひとりでは抱え込まないようにしないと介護者にも介護対象者にも負担が大きくなり両者ともつぶれてしまいますということです。高齢者の介護を続けることで、何かの拍子に自分ひとりで責任を感じ、負担を背負ってしまうことが施設でも家庭でもよくあります。それだけ、介護というのは、ごく一般的に言っても、人間関係がだんだんと閉じてゆく傾向があるといえるかもしれません。
介護に負われていつのまにか閉じて孤立化してしまい苦しんでいるひとは、家庭でも施設でも多いと思います。しかも、その原因は、歴史的な背景や社会構造からきていることが多く、個人だけではとても乗り越えてゆくことが難しいでしょう。(このことについては稿をあらためます。)ただ、三好春樹氏の提案のように、介護にかかわる人間は、まずは、人間関係が外へ開かれた介護環境をイメージすることで、孤立化する危険に深入りしない、力強さをもつことができるのではないでしょうか。 (つづく)
*三好春樹『野生の介護』 雲母書房
*クロード・レヴィストロース 『野生の思考』 みすず書房
|
転載について
日刊ベリタに掲載された記事を転載される場合は、有料・無料を問わず、編集部にご連絡ください。ただし、見出しとリード文につきましてはその限りでありません。
印刷媒体向けの記事配信も行っておりますので、記事を利用したい場合は事務局までご連絡下さい。
|
|
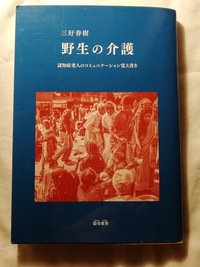
『野生の介護』





|