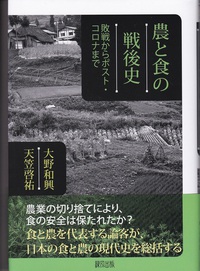戦後75年の日本の農と食の現在地を確認し、私たち一人ひとりがこの問題にどう向き合うべきかを、二人のジャーナリストが現場取材を踏まえて語り合った本書は、すでに日刊ベリタでくわしく紹介されている(注)が、私はそこではあまり多く触れられていない点について考えてみたい。それは、「戦争と食糧は切り離せない」という大野さんの指摘である。具体的には、日本の食糧農業政策が日米同盟とセットになって進められてきた事実である。(永井浩)
▽日米同盟によって歪められる日本の農業
敗戦後の日本の復興のために食糧問題の解決は急務の課題の一つだった。そこで日本を占領統治した米軍は学校給食はじめ様々な支援策を講じたが、1952年の独立回復後も食糧は米国の対日政策の大きな柱でありつづけた。そしてそれは、農業大国である米国の国益と日本の防衛力強化とからめて進められた。
東西冷戦の激化に対応して1954年に調印された日米相互防衛援助協定(MSA)は、米国が日本に兵器その他の援助を約束したものだが、協定は相互防衛援助協定、農産物購入協定など四つの協定からなる。米国は余剰穀物(小麦、トウモロコシ)を食糧不足の日本に送るが、日本政府はその代金を、米国に支払うのではなく、国内で積み立てて防衛産業育成や米軍基地の援助に使うのである。同年に防衛庁設置法、自衛隊法が公布された。
1960年に改定された日米安全保障条約では、軍事面で対等性がやや加わったと同時に、経済条項が入った。日米間の経済関係で食い違いが出たときは、お互いに調整しあうという条項だが、「当時、日米の力の差は圧倒的でしたから、調整といってもすべて米国の言い分を飲むという結果に終わります。農業大国である米国はつねに余剰穀物を抱え売り先を探していました。日本はその格好の市場となった。軍事と経済を絡めて迫られると、断れないのです」(大野)
その結果、日本政府はコメは自給するが、他の小麦、大麦、トウモロコシ、大豆といった主要穀物はすべて米国からの輸入に頼るという食糧政策をとることになった。安保改定の翌年61年に施行された農業基本法は、それを「選択的拡大政策」という形で農業食糧政策に組み込んだ。「こうして日本は(米国の)核の傘と食糧の傘の二つの傘に守られるという戦後体制が作られた」(同)。
そしてその代償として、日本の食糧自給率はいびつさを増し、農業生産構造は深刻な変貌をせまられることになった。
コメへの偏重により、麦の安楽死政策がとられた。この列島の風土が作り上げてきた米麦二毛作が崩壊し、日本の田んぼはコメ単作になり、農家は「コメ+兼業」という形態が一般的となる。さらにコメ過剰の発生、減反が追討ちをかける。
その一方で、米国の安い穀物をエサにすることで成立する工場型の大型畜産が採卵鶏、肉鶏、養豚、肉牛ではじまり、野菜や果実でも大規模化と施設化が進む。
「以前の日本の農業は理想的な農業の形だった。お米が表作、裏作に小麦を作って、それでいわゆる家畜も少し飼って、果実も少し作って、野菜も少し作って。家畜の糞を堆肥に使うなど自然循環の中で無駄なく行っている。小さいけれどきわめてエコロジカルな仕組みの中で、農業というのは営まれてきた。それがいわゆる小規模家族農業の単位だった。それがどんどん崩されていく形になってしまうのが、選択的拡大というものです」(天笠)。
いまや、「農業技術の主体が農民から資本になってきた」(大野)。それとともに、土と太陽光と種子との付き合いの中で人間が知恵をしぼって育んできた食は、人間の手を離れた大資本の工場生産に任され、種子も米国などの巨大アグリビジネスに独占されようとしている。利潤優先の大企業の食製品生産が自然を破壊するだけでなく、私たちの食の安全を脅かすケースは増えつづけている。
さらに、日米同盟の強化を旗印に安倍政権が推進し、菅政権が継承しようとしている経済政策にも戦争と食糧との危うい関係が透けて見えないだろうか。大野さんは「アベノミクスは結局、経済の軍事化だと思っている。経済だけじゃなく、科学技術とか文化とか教育とか、全部を軍事化していくという流れの真ん中に座っているのが安保法制だと思う」という。武器輸出と原発輸出がTPP後の日本の経済を推進する大きな柱とされ、農業特区も設定された。農業も国家による管理強化で軍事化がすすむ恐れがある。
▽食の安全と戦争は相容れない
さてそれでは、食糧の安全保障をおろそかにして、日本の農業を切り捨て、食の安全を脅かす流れに私たちはどう対抗すればよいのか。まっとうな農と食を取りもどすことは可能だろうか。現場で長年この課題と取り組んできた大野、天笠の両氏は、将来にたいして悲観的でも楽観的でもない。軍事化に進む国家の管理強化と大企業の利潤追求のネットワークにからめとられずに、食の安全と農の自立をめざすたたかいが各地で生まれようとしているからだ。
詳しくは本書で読んでいただきたいが、一例だけあげれば山形県置賜の自給圏構想が動き出している。旧米沢藩に位置する三市五町の百姓衆や生協、一部首長、教育界、豆腐業界、旅館業、商店街などが加わり、農地、森、水といった地域資源が生み出す食とエネルギーを地域でまわし、外の世界にも開かれている社会と経済の仕組みを作ろうという試みである。安全で美味しい食をもとめる都市住民と有機栽培の農産物を提供する農村との提携も、各地に広がっている。それらはまだ、実験の域を出ていないとはいえ、やがて列島の隅々で発展し、さらに海外のおなじような動きとの連携のネットワークをつくりあげていくことも夢ではないだろう。
大野さんは「国家を越えて都市どうし、地域間のつながりで資本のグローバリゼーションに対抗しようというものだと、僕は勝手に理解しています」と述べている。
いうまでもなく、食は私たち人間の命の源泉であり、農は自然の一部である人間が大地と共生しながら食をつくりだしていく営為である。また平和な社会なしには、農業は成り立たない。いっぽう戦争は、人間の生命の抹殺が最大目的であり、そのためには食を生みだす自然の破壊もいとわない。本来両立しえない二つを国づくりの政策の柱にしようとすれば、矛盾が生じないはずはない。米国に従属した軍事的な安全保障ににからめとられて、食糧の安全保障は放棄され、農業は疲弊する。
だとすれば、食の安全と農を人間の手にとりもどす動きは、生命尊重を原点としているから、武力による生命の抹殺を目的とする戦争の動きに歯止めをかけ、真の平和な世界の創造につながっていかざるを得ないのではないだろうか。農に内包されている平和の種子が花咲くだろう。そんな期待感を、本書は私にいだかせてくれた。
『農と食の戦後史──敗戦からポスト・コロナまで』は緑風出版から刊行
注:http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=202010300032055
|